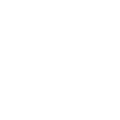1 納税者甲社の主張
1 納税者甲社の主張
甲社は、本件詐取行為の事実を知り得たのは平成16年の税務調査以降のことで、それまではこの損害を知り得ず、損害賠償権の権利行使も期待できないので、益金に計上する必要はない。すなわち、損害が回収されればその時に、そうでなくても、損害発生や加害者を知ったときの事業年度に計上すれば足りる(異時両建説)から、この処分は違法であるとして、東京地裁に提訴した。
東京地裁は、甲社の主張を全面的に認容し、損害賠償請求権の益金計上が、損金算入時期と同時期にされる必要はなく、権利行使の実現可能性が高まったとき、すなわち甲社が損害の事実及び加害者等を知り、回収努力の開始が期待できる事業年度に計上されるとした。
(東京地裁平成20年2月15日判決→納税者勝訴)
Y税務署長はこれに対して、東京高裁に控訴した。
2 「通常人基準」でバッサリやられる
東京高裁は「他の者から支払いを受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金に算入する」(法人税基本通達2-1-43)の規定は、当事者間に争いがある場合の損害賠償責任を想定したものであるため、他の者と限定している。したがって、本件のように、法人の使用人に対する損害賠償権は上記通達の対象外であり、原則通り損金計上と同時期に計上すべきであるとした。そして、損害賠償請求権の計上時期については「通常人基準」によるべきとして、Aの隠蔽、仮装行為についても、甲社はこれを容易に認識・防止することが可能であったことから、Aの行為は甲社の行為と同視することができるとし、法人税の更正処分及び重加算税の賦課決定を適法として、原判決を取り消し、納税者の請求を棄却した。(東京高裁平成21年2月18日判決→納税者敗訴)
3 重加算税まで賦課されることへの疑問
まず、「通常人」というあいまいな基準が飛び出してきて、これに対する明確な定義がないことが疑問である。
さらに、重加算税賦課の要件は「納税者が課税標準、税額の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、それらに基づいて、税額を過少に申告したこと」(通則法6条2項)と規定しているが、第三者の行為が納税者の行為と同一視される場合にも適用されている。すなわち、「納税者と使用人」まで一括りにされるので、会社内で行われた不正行為のほとんどがこの範疇に含まれてしまう。これでは納税者の範囲をあまりに拡大解釈し過ぎてはいないか?使用人が不正を犯した時点ですでに利害対立があり、納税者と同一視すること自体がおかしいと思う。
過去の事業年度に遡って、益金算入された上、重加算税、延滞税を課せられたのでは、「踏んだり、蹴ったり」である。それに、相手先は資力がなく、微々たる債権回収しか得られない。また、わずかでも回収があれば債権を貸倒れとして落とすこともできない。
というわけであるから、ここで経営者は、手痛い教訓を一つ学ぶことになる。つまり、「従業員の不正が、絶対に起こらないように、内部管理体制を徹底しなければならない」という教訓である。