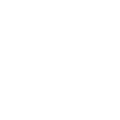今回は前回の過大役員報酬に続いて、過大役員退職金の判定基準はどうして決まるの?というテーマです。
法人が各事業年度において退職した役員に対して支給した退職給与の額が、法人の業務に従事した期間、退職の事情、法人と同種の事業を営む法人で事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、退職した役員に対する退職給与として相当である認められる金額を超える場合おけるその超える部分の金額は、各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入しないとされる(法人税法34?、法令70二)。
税法で否認されないためには、まず最低限の形式基準を満たしておく必要がある。特に、役員報酬や役員退職金に関しては、株主総会や取締役会を開き、議事録を作成しておく必要がある。退職給与規程があることが望ましいが、金額算定の基礎となる功績倍率などは固定化すると危険なので、弾力的に定めておくのが良いだろう。
役員退職給与の損金算入時期は、退職給与の金額が具体的に確定した日の属する事業年度の損金に算入される。株主総会、社員総会の決議、またはその委任を受けた取締役会の決議の時期がその時期となる(法人税基本通達9-2-28前段)。
次に今回のテーマである過大とされる役員退職金の判定基準、つまり言い換えると適正な役員退職金額はどのように算定されるのかというテーマである。適正な算定基準は税法には記されていないが、判例や裁決例によると、功績倍率という算式が基本となっている。
適正退職金額=基準となる報酬月額×勤続年数×功績倍率 という算式である。
基準となる報酬月額は退職年度の月額であるが、急激に上げていたり、逆に非常に下がっていたりもあるので、その場合は、一年あたりの平均額による方法も考えられる。
ここで、最も争点になるのが功績倍率の比率であるが、決まった基準はない。法人と同種の事業を営む法人で事業規模が類似するものだが、どの地域で規模はどの範囲までなのか、サンプル数はいくつなのか?についてまったくルールがない。税務当局が資料として提出する同業種、同規模他社のサンプルの中味はまったく公開されない。これは過大役員報酬のときと同じで、「ポーカーで手の内を見せずに相手を降ろさせてしまう手法である」。
さて、過去の判決例から功績倍率を見てみると、2倍から7.5倍まであるので、どうしてよいのか分からなくなる。東京高裁のS.56.11.18の判例で、社長;3倍、専務;2.4倍 、常務;2.2倍、平取;1.8倍、監査役;1.6倍というのがある。一般的に、この比率が良く基準として使われているようだがこれとて確実なものではない。まあ、代表取締役で2倍から3.倍くらいを目安にあとは貢献度の実質をどのように捉えるかであろう(並外れて優れた創業者であればもっと高くてよいだろう)。
最近では、東京地裁判決(平成28.4.22)が注目されるところである。この判決は、焼酎、泡盛「残波」の酒造メーカー(有)比嘉(ヒガ)酒造(本社を沖縄に置く)の役員4人に支給された、役員報酬及び役員退職金をめぐって、過大かどうかの判断が下されたものである。この事例は、沖縄税務署長が比嘉酒造に対して、すでに支払われた役員報酬を4年間で12.7億円と、役員退職金を6.7億円に対して、約6億円を「不相当に高額」と認定し、更正処分を決定し、約1.8億円の追徴課税を課していたが、これを不服とし、沖縄税務署に異議申し立てをしたが棄却(平成23.11.24)、その後、国税不服審判所に審査請求を行っていたが、これも棄却(平成24.12.18)されたので、東京地裁に取り消しの訴えを起こしていたものである。
この訴えの内容は、法人税法上の役員報酬、退職金に対する基本的な考え方を問うもので、憲法84条(租税法律主義)や憲法31条(正規の法手続き)にも言及している。また、平成18年度改正の趣旨(旧法人税法34条1項、現法人税法34条2項の変更)についても、役員報酬の支給につき利益処分的な意味合いはなくなったと主張、また、役員報酬の算定基準として、従業員の給料を考慮にいれることに対しても反論している。
役員退職金については、当然にその基準となる功績倍率について争われた。税務署側は同業種、同規模他社(売り上げが05倍から2倍までで沖縄と熊本にある会社)の34社分の平均値を基準として資料提供していたが、東京地裁の判断は、同業、同規模他社の最高額を超えない限り妥当としたため、なぜか、役員退職金については適正であるとの判決が下された。その結果、追徴税額のうち0.5億円は取り消された。
しかし、ここで単純な疑問が湧いてくる。
「最初の最高額はどうして税務署に認められたのだろうか?これからもずっとその金額が最高額となり更新されることはないのだろうか?」
「また、同業種の法人にはウイスキーや日本酒やワインの製造元は含まれないのか?」
「対象地域はなぜ沖縄と熊本に限定されるのか?日本全国に及ばないのか?」
などである。
役員報酬については税務署の原処分が覆されることはなかった。法人税法では、役員報酬及び役員退職金は利益処分との考え方が根底にあり、例外的にある条件のもと損金算入を認めている。言い換えると、役員報酬は会社への職務に対する対価と見ているわけであるから、会社の業績が落ちたり、従業員の給料が下がったりすれば役員報酬も減額されて当然という見方である。
役員報酬が、従業員(使用人)の給料を参考に決められるのはいかがものかと思うが、実質基準(法基通9-2-21)には ? 役員の職務の内容 ? 法人の収益 ? 使用人に対する給料の支給状況 ? 同種の事業を営む法人で事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等 とある。
一時期は、空前の焼酎ブームだったが、同業他社の追い上げや日本酒ブームに押され焼酎業界の業績にも陰りが見え始めている。(有)比嘉酒造は従業員40人弱、売り上げ20億円弱ほどの法人であるが、役員退職当時には、売り上げも減少しており、従業員の給料も上がっていなかったのに、役員報酬を急激に上げている。この辺りを、税務署は指摘している。
東京地裁の判決にも、矛盾点は多々あるが、両者の立場の均衡点をはかった結論になっている。特に役員退職金では、納税者側に有利な判定が下ったことは喜ばしい。税務当局も以後、控訴していない。
(追加情報)
その後、比嘉酒造側は、東京高裁に上告したが、棄却され、現在、最高裁に上告中。
文責 増井 高一