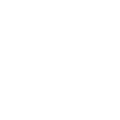1 養老型生命保険の変形型
(死亡保険金受取人;法人、解約返戻金の受取人;個人)
養老保険を利用した過去の節税スキームの一つに、法人甲が個人Aに掛けていた保険を、満期日に保険を解約し、個人Aに一時所得を発生させるというものがあった。この保険商品は、契約者が法人で、被保険者が個人、そして、死亡した時の保険金の受取人が法人で、解約返戻金の受取人が個人という変則的な(通常は死亡した時、保険金は遺族に、解約した時は法人に解約返戻金が入る)ものであった。法人甲は、1/2を貸付金とし、残り1/2を保険料として経理処理していた。
そして実際、満期保険金を受け取った時に、この総額から、法人甲Aが支払った保険料の全額を控除して、それを一時所得として申告していた。つまり、支払保険料の全額が、所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」にあたるという文言通りの解釈をしていた。簡単な例で説明すると以下のようになる。
| <法人> | <個人> | <一時所得> |
| 掛け金 200万円×10年=2,000万円 | 解約返戻金;2,050万円 | |
| 貸付金100万円×10年=1000万円 | 掛け金 △2,000万円 | |
| 保険料 100万円×10年=1000万円 | 特別控除 △50万円 | |
| 差額 | ゼロ | ゼロ |
個人の手取りは、2,050万円から、法人からの借入金1000万円を返済して、1,050万円となる。
法人が支払った保険料が、法人側で経費(損金)として計上されながら、個人の側でも、一時所得から控除できるとすれば、それはあまりにも虫のいい話だと思うのだが、それなのに、なぜか、福岡地裁平成21年1月27日判決、およびその控訴審である福岡高裁平成21年7月29日判決では、Aの主張を認めていた。しかし、結局、最高裁では、原判決が破棄され、更正請求も棄却された。そして、「その収入を得るために支出した金額」とは、一時所得を得るために個人が自ら負担して支出したもので、収入を得る主体と支出する主体が同一であることを前提とするとした。
この最高裁の判決後、基本通達にもそのことが明示されるようになった。(基本通達34-4(1)(2))これで、この手の話は終わりだと思っていたが、もう一つ異なるタイプの保険商品が現れた。
2 低解約返戻金タイプの生命保険
それは「低解約返戻金タイプの生命保険」というものである。この保険は、最初の数年間、解約返戻金は極めて低いが、5、6年目あたりから、急に解約返戻率が上昇してくるタイプの保険である。この節税スキームは、法人が掛けているこの保険を、個人が初期に時価で買い取り(通常保険商品の時価は解約返戻金の額になる)、名義変更を行い、その権利を承継した後、しばらく個人で保険を掛け続け、解約返戻率が上昇したところで、解約するというものである。この時受け取る保険解約金の一時所得について、1とよく似た争いが起こり、札幌高裁に持ち込まれていたが、札幌高裁は最高裁と同じ理由で棄却した。(平成29年4月13日)
医療法人甲とその理事長Aは、医療法人甲で、一旦「低解約返戻金タイプの保険」に入り、Aは保険加入1年以内に、法人から時価(約17%くらい)で買い取った。その後、2回目の保険料を個人で支払った後、解約した。
理事長Aは「平成24年最高裁判決は、養老保険に係る保険料が争われた事件であり、名義変更が行われた本件とは事案を異にする」と主張したが、札幌高裁は「その収入を得るために支出した金額」とは、あくまで収入を得た個人が、自ら負担して支出したものかどうかで判断され、名義変更とは関係がないとした。
それにしても、理事長Aは欲張りな人である。法人が掛けた保険料の全額を一時所得から控除できなくても、低い時価でこの保険を購入した段階で、個人はすでに将来の高い返戻率で解約できることが保証されている。そして、解約金のうち、低い時価との差額について、1/2にしか課税されないのであるから、すでに、十分すぎるメリットを享受していると思うのだが・・・・・。
それに、まだ法人側に問題が残っていないわけではない。この種の生命保険のタイプでは、法人が保険に入った後、すぐに個人が買い取れば、時価で買い取ったとはいえ、法人に多額の損失が発生するわけだから、そのことにつき、法人税法上の問題点(経済人としての合理的な行動ではない)がまったくないとは言えないからである。