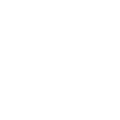1 東京地裁 創業者の退職給与を巡り国側の勝訴
東京地裁は2月19日、搾乳事業、肉用牛の事業を営む会社(原告X社)が、同社の創業者である元代表取締役に支払った役員退職給与約3億円に対し「不相当に高額な部分の金額」あるか否かについて争われていたが、原告の請求を棄却した。東京地裁は、国が抽出した同業種3社の平均倍率「1.06倍」に基づき算定した約4千万円を超える2憶6千万円が「「不相当に高額な部分の金額」に当たると判定した。
この事例について、驚いたことは、原告の功績倍率が「8倍」と極めて高かったことと、これに対し、国側が示した功績倍率が「1.06倍」とあまりに小さかったことで、なんと8割に当たる2億6千万円が「不相当に高額な部分の金額」とされたことである。
この結果、法人側で2億6千万円が損金とならず、役員賞与(利益処分扱い)となったことによる法人税、住民税の追徴税と、さらに個人側では2億6千万円に対して新たに所得税が課される。当然、これらに対し加算税と延滞税が課されるため、その課税金額は莫大なものになる。
2 退職給与についてルールが無さ過ぎではないか?
なぜこのように極端な解釈の違いが生じるのだろうか?
それは、まず法人税法にも通達にも明確な基準ルールが無さ過ぎるのである。実務の世界では創業者の功績倍率は「3倍」くらいまでが適切ではとの常識はあった。
本件では原告の功績倍率が「8倍」もけた違いに大きいが、原告は専門家の助言をまったく受け入れなかったのかと疑問を持つ。
しかし、それにしても「1.06倍」とはあまりに小さい。確かに搾乳事業という特殊な事業に限定すれば、同業類似法人3社の平均値はそうなのかもしれないが、この形式基準には納得できないところがある。
原告の主張の中に、「最終月額報酬110万円」は功績の程度を反映していないというものがある。思うに、X社の元代表の考えは、役員給与は少なめに取りながら、会社の内部留保を厚くするという経営方針を貫いていたのかもしれない。もし、そうであるならば、創業者が蓄積してきた内部留保はかなりの部分は創業者に還元されるべきものと思われる。
これから、役員月額給与を考える場合は、退職給与の功績倍率を考慮して、高めに設定したほうが有利ということになるだろう。
3 国側が抽出する基準について
国側は、いわゆる倍半基準や日本標準産業分類の業種に基づき、同業種法人の抽出を行っている。本件については抽出範囲を管内以外の4つの国税局にも調査依頼している。
- 地域がなぜ限定されているのか?
当然その範囲は全国に及ぶべきである。平均ではなく最高金額が基準となるべきである。
- 同業種の範囲?
同業種だけではなく類似業種にも及ぶべきである。かつて、焼酎製造会社で争われたときは焼酎製造会社に絞られていた。この場合も、日本酒、洋酒、その他飲料水製造会社にまで範囲は広げるべきであろう。
- 倍半基準の妥当性?
倍半基準とは、その会社の年商の1/2から2倍までの会社を抽出するというものであるが、これとて根拠のあるものではない。もっと範囲を広げなければならないと思う。
- 最初の最高額はどうして決まったのか?
抽出した会社の最高倍率は、当初なぜ「不相当に高額な部分」に当たらなかったのか?そのときの最高倍率であるなら他の平均倍率よりはるかに高いはずであるから、「不相当に高額な部分」が含まれていたはずである。
(結論)
「なんとなく3倍」ではあまりに曖昧であるし、「業種によっては1.06倍ですよ」では、まるで、「闇討ち」にあったようなものである。
いずれにしても、過大役員報酬の判定基準については、根本的な議論を尽くし、本件のような極端なギャップが国税当局と納税者の間で起こらないように、法令化することが望まれる。
私たちは民主主義の法治国家に住んでいる。「租税法律主義」(憲法31条)「正規の法手続き」(憲法31条)に則って、税金の徴収は行っていただきたいと思う。